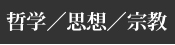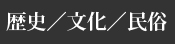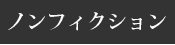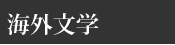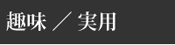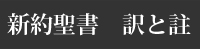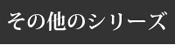日本人の死生観 第一巻
霊性の思想史

鎌田東二
本体2,700円
ISBN 978-4-86793-076-2
発行 2025.3
【内容】
日本人の「いのち」は死後どこへ行くのか。
汎神論と習合思想の土壌に醸成された 独自の世界像を
『記紀』『万葉』から探る「たましい」の 精神史。
わがみちを
どこまでいけども
はてしなく
とほうにくれて
みちなきみちをゆく(東二)
「いのち」は生と死の両極を含み持つ言葉である。たとえば、『万葉集』に見られる「いのち」にかかる枕詞は「たまきはる」であるが、それは、「魂・来・経る(膨る・張る)」、すなわち「魂が来訪して膨らみ経ていくもの」の意味で、魂の来訪と通過を核として成立している。とすれば、「いのち」の中には「たま(たましい)」をも含んでいるということになるだろう。そのような日本人の「いのち」観に基づきながら、「環境・生命・倫理」について神道の立場から考えてみたい。(本文より)
【内容目次】
序章 安部公房と三島由紀夫の比較から始める
1 安部公房と三島由紀夫の「日常」と「非日常」の交錯と変容
2 明治と昭和の戦争世代論
3 安部公房の場合
4 三島由紀夫の場合
5 「二つのドングリ」安部公房と三島由紀夫
補記 梅原猛の三島由紀夫論
第一章 「霊」あるいは「霊性」の宗教思想史
1 はじめに
2 樹木のメタファーと問題意識
3 縄文の霊性と木と石と貝
4 「むすひ」という霊力
5 『古事記』と『日本書紀』と『日本霊異記』の中の霊木信仰
6 「霊威」の位相学
7 『源氏物語』とモノノケ
8 モノノケと猿楽・能と神楽
9 中世霊性論――神道的霊性
10 上田秋成の「霊異」譚と平田篤胤の「霊性」観想
11 近代の霊性探究
12 現代の霊性探究
13 今、ここでの死生観探究
14 おわりに
第二章 うたといのりと聖地の死生観
1 はじめに
2 聖地の生物学的・惑星的基盤
3 聖地の特性
4 「うた」はどこで歌われたのか?
5 どこで、「いのり」が捧げられたか?
6 「聖地」としての「神社」の存在理由
7 延喜式内社と大和国の式内社
8 日本の都城と聖地
9 「聖地」としての三輪山と磐座信仰と箸墓と「ホト」のシンボリズム
10 『万葉集』と三輪山
11 歌の始まりと歌の力――むすびにかえて
第三章 いのちをめぐる東西の自然理解と死生観――環境・生命・倫理〜神道の立場から
1 「いのち」と「命主社」――出雲神話から探る
2 「いのち」と「むすひ」――『古事記』における「成れる神」と「生まれる神」
3 「神道」とは何か?
4 一つの具体例――「鳴鏑を持つ神」
5 いのちの言葉としての「言霊」という事例
6 「汎神論」と「アニミズム」――現代日本人の「自然理解」の二つの視点
第四章 モノと霊性――ものづくりからもののあはれまで
1 仏像展の「モノ」(ものざねから物の怪まで)の死生観
2 わが国最初の仏像と木の霊力
3 ものづくりと手わざ
4 「もの」の本義とグラデーションと霊性
終章 言霊と神道――草木言語から人間言語・地域言語への射程
1 根っこ
2 言霊概要
3 草木言語
4 和歌即陀羅尼説
5 オノマトペ
6 神道概要
7 神道と仏教との対比とその融合
初出一覧
参考文献
あとがき――出雲系死生観
補記 出雲魂ルネサンス